ブログ小説「冴子の人生は」その65まで
「冴子の人生は」節目節目で
大きく変わっていきます。
人生が
大きく変わると
悪い方にかわる方が
多いかもしれませんね。
冴子には
モデルがあります。
多くはフィクションですが
冴子の
人生の最期ー最大の不幸は
ノンフィクションです。
もっと
、、、、、、
、
その64は最後の方です。
冴子の曾おじいさんは 兵庫県の篠山の 大地主でした。 戦争に負け 農地解放で 普通の農家になった 冴子の おじいさんは よく働きました。 その息子の 冴子の父親は 次男坊だったので ある大手の重電メーカーで 生涯働きました。 冴子は 昭和25年に 3兄弟の 真ん中に生まれました。 重電メーカーの 社宅で育った冴子は 普通の女の子でした。 成績は 中くらい 目立つようでもなく 目立たないようでもない そんな小学生 中学生でした。 中学生の時 同じクラスの 男の子に 好きになりました。 席が隣で 何となく 不良ぽいところが 冴子の 気を引いたのかもしれません。 その男の子は 冴子を ぞんざいに扱いました。 気があったのかもしれません しかしそれは 冴子の思い過ぎだったんです。 冴子の 最初の悲劇は オリンピックの翌年 起きてしまうのです。 その男の子が 何を思ったのか 冴子の 制服の フレアスカートを めくったのです。 クラスメートの前で 、、、 男の子は 別に 大した意味もなかったのですが マンガの影響で 当時はやり始めたのです。
当時はやっていた スカートめくりに対して 女子は ブルマを常時はいて 対抗していました。 しかし 冴子は 母親の 不手際?で ふたつとも洗濯していて 履いていなかったのです。 そのためお調子者の 別の男の子が 「白パン!」と はやしたてたのです。 この問題は すぐに 担任の知るところとなって 男の子は 厳重注意され 双方の家族に 連絡がいきました。 受け取った 冴子の父親と母親は これ以上 問題を 大きくしたくなかったので 冴子に 我慢するように 言いました。 相手の男の子が 会社の 上司の 子息だったのです。 冴子は それを理解していましたので 何も言えませんでした。 でも 冴子は 学校に行くのを 嫌がるようになりました。 両親は 高校は その男の子が 絶対に行かない 女子校にするからと 言って 冴子を 説得しました。 そう言うわけで 冴子は 近くの 市立高校に行かず 一駅向こうの 私立の女子校に行くことになりました。
社宅の 噂は すぐに 広まります。「部長の不良息子が 部下の 娘に 手を出した」という 事実とは 全く違う 噂が 本当の話のように 広まりました。
でも その噂は 表沙汰になることはなく 付近の人たちの 心の中に ながく 記憶されることになります。
噂の内容が 間違っていることを みんなに告げることも出来ず 加害者被害者は 弁解する機会もなく 時間が経ちました。
冴子は 被害者としての立場より 好きだった人に 裏切られたという思いだけが ずーと 記憶に残っていくのです。
冴子は 事件が起きたのが 3学期であることだけが 救いだと思いました。
卒業して 新しい高校に行けば こんな記憶は 消えてしまうと 思ったのです。
残りは ほとんど出席せず 卒業しました。
部長も 春の移動で 本社の移動したので その不良息子と 出会うこともなく 良かったと 思いました。
女子校は 男子がいないという以外に とても厳しい進学校でした。毎回のテストは 必ず席次が発表され 冴子は そのことが とても つらかったのです。
それから クラブ活動は お茶とお花 それに 作法が 全校生徒 必ず参加することになっていました。
冴子は 正座が 子供の時にケガをした関係で 苦手で 嫌でした。
冴子は 電車に乗って 通学します。
電車は いつも同じところに乗るのですが 同じように 前の席に 男の子が 乗っていきます。
何となく不良ぽいその男の子を 気になっていました。
詰め襟の ホックを 外して 第一ボタンも 外しているのです。
昭和40年代の初めの頃なので そんなことをする 学生は いません。
「不良」以外には 考えられないのです。
冴子は 毎日見かける その男が ずーっと 、、、、、
当時の 高校には 厳しい校則があって とても 恋愛は出来ません。もし校則が許しても 冴子は 自分から その男の子に 声など掛けられるはずもなかったのですが 校則が うらやましく思っていました。
その男の子は 冴子乗る電車に既に乗っていて 冴子が 次の駅で降りても 乗っていました。
いろんなことから その男の子は 冴子が下りる 次の次の駅の 高校の生徒であることがわかっていました。
冴子の女子校が 創立記念日で 休みだった 7月のある日 私服で 同じ電車に乗ってみました。
ドキドキしました。
その男の子は いつものように ボタンを外して 電車に乗っていました。
次の駅で降りず 次の次の駅で 冴子は 降りました。
その男の子は 電車を降りる前に ボタンを留めて 詰め襟をとめて 帽子を 正しく被って 改札を出ました。
学校に着くと 校舎の中に 消えました。
男の子の後を付けて 高校まで つけていった 冴子は 胸がドキドキしました。
不良ぽくない まじめな男の子を見て もっとドキドキしました。
冴子は その変わり身の早さに びっくりしました。恋心からではないと言ったら 嘘になりますが 帰りも見たくなりました。
それで 下校時も 見たい気分に なりました。
そこで 3時頃まで 近くで 時間をつぶすことにしました。
当時は ショッピングセンターがあるでなし コンビニがあるでなし まだ図書館も出来ていなかったので 公園で 待つことにしました。
昼日中から 高校生が 公園にいると 不審に見えるらしく 警察官に 職務質問されたりしました。
創立記念日で 休みと言ったら 無線で 問い合わせされてしまいました。
昼は 近くの パン屋さんで あんパンと 牛乳を買って 公園のベンチで 食べました。
付近の人は きっと変と思っているだろうな と考えると 笑いがでてきました。
3時前に 校庭の見える 正門の近くの 木の陰で 待っていました。
そうすると その男の子らしい人影が 校庭に見えました。
その男の子は 白いユニホームで 校庭に勢いよく出てきて 白いボールを キャッチボールするのです。冴子は 電車に乗っている時と 全く違う その有様に 驚きました。
冴子は 何か裏切られたような しかし 何となく気になるよな 不思議な気持ちになりました。
その日は あまり帰宅が遅くなると 親に不審がられるので それを見て 帰りました。
家に帰って 頭の中を整理して でも 整理できずに 訳の分からないと 考えました。
そんなもの考えても仕方がないの そう考え直して やっぱり 一途でいこうと 思いました。
翌日から いわゆる追っかけのようなことを していました。
今で言えば ストーカーです。
でも 校則は恋愛禁止 校則に違反すれば 両親に 心配することになるので 校則に違反することはできないと 思っていました。
それで 卒業したら 告白しようと 考えました。
それまでは 不良ぽっく それでいて まじめな 男の子を 一途に 思い続けることを決め そのようにしました。
現代なら こんな事はないと思いますが 昭和40年はじめの頃の お話です。
そのようなことは あったと 考えて下さい。
一途に 思い続けて 2年余経ちました。彼の実家も 家族構成も わかっています。
彼に 女性の影がないことを いつも確認していました。
彼が 大学に進学することがわかっていましたので 冴子も 大学に進学したいと 思っていました。
それなりに 勉強していて ある程度の自信はありました。
両親に言うと 兄が私立大学に進学して 冴子も 私立高校だったので 私立の大学なら 余裕はないと 言われてしまいました。
私立の高校に行ったのは 私の責任というか 責任でないというか ある程度 諦めました。
親の言うのも わかりますので がんばって 公立に合格すると 決意しました。
それなりの勉強から がんばる勉強に 変わって クラスメートを 驚かせました。
もちろん 彼を 一途に思っていましたが ストーカーは しばらく お預けでした。
そんな毎日も 電車の中で 彼を見ていました。
昭和40年はじめの頃の 大学受験は 団塊の世代を迎え 狭き門です。公立は 旧帝大の一期校 地方の国立大学の二期校 それに 県立府立私立などの中間校 の三種類です。
とても とても 一期校は無理なので 中間校と 二期校を 目指していました。
その名の通り 試験は 一期校から始まり 中間校 二期校となります。
冴子は 公立一本ですので 中間校と 二期校を 二回受験することになります。
冬の寒い日でした。
体が温まるようにと 朝食に お肉を食べて 自宅を出 電車に乗りました。
いつもの電車より 1時間も早いので すいていました。
彼は絶対に乗っていないと 思っていた冴子ですが イスに座って 問題集を出して 最後のチェックをしようと 目を上げたとき きっちりした制服姿の 男の子が 目に入りました。
「えっ 彼だわ
なんで何でよ」 と思いました。
そして もっと 衝撃的だったのは セーラー服の女性が 隣に座って 楽しげに 話していることでした。
「嘘でしょう そんな事ないでしょう何なの どういう事なの」 と 冴子は 伏し目がちで 彼を見ました。
冴子だけ 時間が止まり 何も考えられなくなりました。
今までには 見たことがない光景です。
その セーラー服の女性が どのような関係か 彼とのやりとりを見ていると すぐわかりました。
少なくとも 兄弟ではないと わかりました。
彼は 冴子のことを いつものように 気付いてはいませんでした。
彼は学校のある 駅で降りて いきました。
もちろん セーラー服の女性も 後を追うように ついて降りました。
昨日は いつものように ホックを外して 乗っていたのに なぜ今日は こんな早い時間に ふたりで乗っているのか 違う人じゃないかと 疑いましたが。 どう見ても 同じ人のように見えたのです。
彼の家族は 調べていますので 双子の兄弟とかではないことは 明らかです。
同じように降りたくなりましたが 我に返って 座っていました。
冴子は 大切な 大学受験の日に この様な 事が起こるとは 理解できませんでした。もし受験の日でなければ ついていった その真相?を 究明するのに と思いました。
でも 今日は 大学受験の日 残らざる得ません。
なぜ なぜ なぜと 繰り返しました。
試験場についても そのことが 頭から 離れません。
試験が はじまり 何とか 問題に 専念しようとしました。
試験中は 無になるような 感じがするのですが 今回は そんな感じを 受けないと 冴子は思いました。
問題に熱中できない と感じながらも 電車で見た 彼を 考えてしまうのです。
一時間目二時間目三時間目 熱中できないまま 昼の休憩時間になりました。
家で作った 弁当を 試験場で 頂きました。
外は 強い風が吹いているようです。
熱中しようと思っていますが 熱中できないのです。
そんなジレンマが 余計に イライラさせて 冴子は もうダメだと 思いました。
しかし 最善を尽くせと 父にいつも言われているので 午後の時間も がんばったつもりです。
そして 終わって 帰る途中 遅くなっていましたが 彼の 学校の 駅におり 少し待っていました。
でも もう暗くなってきて でも 待っていました。
真っ暗になっても 彼は来ない 遅くなると 家族が心配するので 帰りました。
家族には 勉強で 図書館に寄っていたと 嘘をつきました。
笑顔で がんばっていると 話しもしましたが、 ベッドの中に入って 涙が出てきました。
受験の結果は 火を見るよりも明らかです。公立の大学に いけなかったら 就職するしかありません。
中学校の同窓生の進路が 同窓会で 明らかになっておりますが 大学に進学する人は 15パーセント程度で 就職するのが 一般的でした。
女性なら 事務職が多く 簿記や珠算ができることが 条件です。
冴子の 高校は 進学校で 特に 選択しなければ 簿記の授業はありません。
冴子は 珠算は 小学校の時 3級まで 練習しましたが 途中で止めました。
冴子が 2月の終わりから 就職活動を 始めましたが 銀行や 公務員などの 求人は もうありませんでした。
両親は とても 心配して 父親は 会社の 上司に頼みました。
当時の 就職は いわゆる コネが 幅をきかせていた時代でしたから 父親が 頼みに行くのも 当たり前のことです。
上司の 「つて」から 重電メーカーの 関係会社で 中堅の 電機部品会社の 工員として 就職が決まったときは 冴子の 家族は みんなで お祝いをしました。
こんな事になった 原因である 男の子が なぜ その日から 朝早く 登校することになるのかは 十数年後に わかるのですが 当時の冴子は 知るよしもありません。
冴子は 試験日のその日から 男の子に会っていませんし 会おうともしませんでした。
冴子が勤め始めたのは 昭和44年の春です。冴子の社宅から 自転車で いけるくらいの距離にあって 当時テレビには 絶対必要なもの テレビチューナーを作っている会社でした。
ロータリーチューナーで 親会社に 納品にしていて 景気がよい会社でした。
そんな会社に 工員として勤めた冴子は 同僚先輩から 少し浮いていました。
その会社の 工員たちは 中卒の生え抜きで 高卒の冴子を 仲間はずれにしていたのです。
そんなことがわかって 会社は あまり人と関わりのない 検査部門に 冴子を 配属しました。
会社の製品である チューナーの出来を 検査するのです。
検査用の機械に 取付 チューナーを 回して 問題なく テストパターンが 映るかどうか検査するのです。
当時は カラーテレビが出始めた時期で カラーの テストパターンを 見続けていると 残像が残って よくわからないようなことが 起こってしまいます。
冴子は 上司に言われたとおり 手順書どおり 検査をして 冴子の検査印を 押して箱に詰めました。
一日中しても いや一ヶ月しても 一年経っても 不良品なんかは 見つからないのですが 検査は 粛々とするのが 冴子の仕事でした。
冴子は 会社には満足していました。検査の仕事も 冴子の検査印を押さないと 製品にならない 重要な仕事と考え やり甲斐のある仕事だと 思っていました。
冴子の会社は 品質管理運動が盛んで 冴子も 検査方法について 提案して それが実行され 報奨金をもらったこともあります。
一年経ったとき 冴子の 父親は 京都の子会社の 課長職へと 栄転になります。
冴子の父親は 変圧器の製作一本で 働いてきて その製作法は 特許にならないまでも 相当利便性が高く 会社に評価され 栄転になったのです。
当時の会社は 専門職を作るのではなく 総合的な力を 作るものでした。
と言うわけで 冴子は 京都から 会社へ通勤するか 会社の近くで 一人暮らしをするか 選ばなければならなくなりました。
父親は 2時間弱かけて 通勤するよう 言いました。
母親も心配して そう言ったので 冴子は 電車で 会社まで通うことになりました。
3度乗り換えて 通勤は 少し疲れましたが 慣れれば さほどでもないと 思うようになりました。
通勤に時間を要すようになってから 冴子は 仕事が終わると すぐに 電車に乗って 帰宅の途についていたので 会社での 飲み会などには ほとんど出席することはありませんでした。
ブログ小説解説編普通は ブログ小説の中で 主人公の立場や心情を 表現するのでしょうが 未熟な私には そのようなものは かけないので より 冴子の状況を 知ってもらいといと思います。
冴子の生まれたのは 昭和25年です。
私の 女房殿の生まれた年と同じです。
冴子の父親は いわゆる工員さんで 社員さんではありません。
現在はそのような言葉は 死語になっていますが 工員さんが青色の作業着を着て 青い襟であることから ブルーカラー と呼ばれていました。
ブルーカラーの 対語は ホワイトカラーです。
ホワイトカラーは 社員さんと呼ばれ 退職金や年金があって お給料も月給制です。
ブルーカラーは お給料は 日給月給制 普通は退職金や年金もない方が多く 有っても少額です。
でも 働いている限りは 必ず 1ヶ月に1回 現金が入ってきます。
その額は 冴子が 小学校に行く 昭和30年初め頃なら たぶん1万円程度ではなかったかと 思います。
冴子の家は 今の基準で言えば 相当貧しい いや赤貧といった方が良いかもしれません。
しかし当時なら 普通か ほんの少し豊かだと思います。
私の家は 農家で 現金収入がなかったので 工員さんの家より 相当貧しく 誰が何と言おうと 赤貧だと思います。
私の女房殿の家は 大地主の家だったのですが 贅沢とはほど遠い生活を 慎ましい生活をしていたそうです。
女房殿の 話を聞くと 私より 相当 豊かだったように思います。
誤解されたら困りますので あえて言っておきますが 私の家は貧しかったですが 家族のおかげで 私は 大変幸せでした。
ブログ小説解説編 その2平均的な 生活をしていた 冴子です。
でも 社宅という 殊な環境で 育った冴子です。
幼稚園は 市立の幼稚園です。
一年だけ 行きました。
2年行く人もいましたが 母親が 専業主婦だったので 行きませんでした。
専業主婦が 普通だった 当時 幼稚園は 一年だけが 断然多いです。
小学校は 近くの 市立小学校で 団塊の世代で 多くなっていて 戦争で 燃えなかった講堂まで 仕切って 教室にしていました。
幼稚園でもそうですが 給食があって 校舎内に 調理棟があって 給食係が 大きな容器と アルミの食器を 教室に運んできました。
給食は クラスの大方の人が 好きで 競って おかわりをしました。
よくでた給食のメニューは トマトと豚肉を煮たもので 洋風の名前が付いていましたが 冴子には ケチャップ煮と思っていました。
大きくなってからも なぜ あれが毎日のように 出たのかわかりませんでした。
それから ミルクです。
牛乳ではなく ミルクなんです。
そう呼んでいました。
冴子が 4年生の時までは 脱脂粉乳を お湯に溶かしたものだったのです。
すこし くさいような臭いがする 飲み物ですが 少数の人を除いて 好きだったようです。
冴子も好きでしたが おかわりは しませんでした。
ここより 小説に帰ります。冴子は 検査端一筋に 3年勤めた春 冴子の父親は 本社の課長へ 栄転になります。
実直な 父親が 課長になるのは当然と まわりの人は 思われていました。
今度は 社宅ではなく 小さいですが 一戸建ちを 父親が買ったのです。
二階の小さなお部屋でしたが 初めて個室を持てて 冴子は 嬉しくなりました。
会社に近いので 朝はゆっくり起きて 会社に歩いて行きました。
そんなある日 検査をしていて 問題のある製品を見つけました。
今まで そのようなことがなかったので 再度検査し 更に 検査具が 故障していないか 調べましたが やっぱり 検査要領書では 出荷不可になる製品でした。
初めてのことなので 検査要領書に書いてあるように 製品に初めて使う不合格印を押し 検査報告書に 不合格製品1と 記して 検査日報を 上げました。
検査の所属長は 製造部門の課長が 兼ねていて 検査日報を 見ずに 印を押して 製造部長のところに 一週間分まとめて 提出されました。
不合格製品は 検査要領書の通り 不合格製品棚に置き その日の検査を終えました。
初めて経験した 不合格のこの製品が 週明けの 月曜日 大きな問題になるのです。
翌週 仕事を始めようと 準備していると 部長から 突然呼び出されました。部長室に行くと 課長や 製造の係長はじめ 製造を担当した女工5人が待っていました。
冴子は 朝の挨拶の中で 製造部長が 「不合格品は本当か」と いきなり聞いてきました。
冴子は 「報告書の通りです」と 答えました。
部長は 製造課長や 係長に どのような問題で この様なことになったのか 厳しく問いただしました。
係長や 製造の担当者は 平謝りで 痛々しいほどでした。
特に女工の面々は 隅で小さくなっていました。
なにしろ 何年間も 不合格品を出していないことが 誇れるもので 納品会社にも そのように報告していたのです。
その信頼が 会社の業績になっていると みんなはそのように考えていました。
冴子は 検査員として 職務をしただけですが こういう結果になって 驚いていました。
でも 理不尽ですが もっと 大変変なことが 冴子の身に起きてしまうのです。
冴子の会社は 品質管理に 凄く厳しかったのです。その当時では 珍しい 工程時検査を していました。
もちろん そのような 厳しい検査をしていても 不良品が 出てしまうことも 確率的にはあります。
そこで 製造部門と 検査部門の 申し合わせがあったのです。
即ち不合格品があると 検査をしなかったとして 製造部門に 戻すのです。
検査をしていないので 検査部門にも 問題がなく 戻された製品は 再度検査して 不良品ははねる手はずとなるのです。
その申し合わせは 検査要領書に 書かれていませんでしたが 当然のことと 製造部は思っていました。
冴子は 検査部門に配属になったとき そのような申し合わせがあることを 聞いていませんでした。
でも 聞いたいなかったので そのような結果になったと 製造部門の面々は 思っていませんでした。
冴子と 製造部門の 女工さんとは 仲が悪かったので そう思われたのかもしれません。
冴子は 正しいことをしたのに 社員の大方は そうは思わず 冴子を 責めたのです。
しかし会社の上司は そのようなことは知らず 会社の雰囲気は 冴子にとって 最悪の結果となります。
一部の上司は 内容を知っていましたが 表面化はせず そのことが 余計に 冴子を苦しめました。
でも 冴子は 割り切って 職務を 粛々と こなすしか有りませんでした。
冴子は 会社の近くに引っ越して来た 春からは 会社の作法クラブ 入っていました。お茶やお花 お琴やお料理まで 種々ことを 習うもので 花嫁修業とでも言うものでした。
会社の 福利厚生費から お金が出ていて 結構 いろんな事ができました。
でも あの検査のことがあってから 居づらくなって 冴子は行かなくなりました。
ただひとり 検査の機械だけを 相手に仕事をしている 冴子は 我慢するしかなかったのです。
そんなことがわかっている 上司の中には 冴子を 可愛いそうに思うものも いました。
今では 考えられませんが 仲人のようなことを やっていたのです。
個人情報保護法で そんな慣習は、 消え失せてしまいましたが、 当時では当たり前のことです。
課長が そんなことに 積極的な 専務に言って 専務の奥様が そのネットワークを駆使して 相手を探すというものです。
冴子の 趣味はもとより 家族や 親の仕事や地位収入まで その情報が 奥様のもとに集まっていたのです。
個人情報保護法なんて言うものは 全く意識されていない時代です。でも 普通に 庶民は 暮らしていました。
ないことが よかったかもしれません。
しばらくすると 人のつてを 頼って 冴子の 父親のところに 見合いの話が 持ち込まれたのです。
家に帰ると 父親は 冴子を呼んで 見合いのことを話しました。
会社関係の 頼み事ですので 冴子を説得しました。
冴子は まだ22才になったばかり まだまだ結婚しようとは 思っていなかったのです。
当時は 22才は 適齢期と考えていましたので 見合いだけはすることに なりました。
見合いは 次の日曜日 冴子の両親と一緒に 近くの ホテルで行われることになりました。
冴子は そのホテルには 初めてだったので その方が 興味でした。
冴子は 中学校の友達は 例の事件があって あまり近づけなかったのです。
高校の友達は 大学に進学していて 故郷を離れた人も多く 今もつきあっている 友達もいませんでした。
もちろん職場は そんな状態ですので 見合いのことを 相談するのは 両親しかいなかったのです。
両親は 見合いをすすめました。22才になるので 結婚する必要があると 両親は 思っていました。
冴子は まだ結婚する気にはなれなかったのですが 両親をはじめ 上司が すすめるので 会ってみようかと 思いました。
それに あのホテルの 食事も食べたいと 軽い気持ちで 見合いをすることになりました。
見合いは 普通 何度もして 何回かの内で 決まることとなるのです。
そんなことがわかっていたので 冴子も 「やすやす」と 見合いをすることになったのです。
日曜日になると 前から用意してあった 振り袖を着て ホテルに出かけました。
もちろん初めてあった その男性は 川本登と言って 冴子の家に住んでいて ちょっとお金持ちでした。
パリッとした 三つ揃いのスーツを着ていて 母親は その当時では珍しい 指輪・首輪・耳輪をしていました。
そんな 男性と 話をするより 初めての フランス料理の方が 冴子は 興味があって 下を向きつつ しっかりと 食べていました。
仲人となる父親の上司は 相手の男性に いろんな事を 聞いていました。仕事の内容とか 今日は来ていない 家族のことなどを 聞いたのです。
冴子の代わりに 聞いていると言えば 聞いているのかもしれませんが 単に 興味から聞いているのかもしれませんでした。
冴子は 男性の話の内容については 聞いてはいましたが 気にはとめませんでした。
仲人は 冴子にも 聞いてきましたが 大方は 冴子の父親が 答えました。
冴子は 「はい」と 言ったのが 数回です。
小一時間 そんな話が 続いたのですが 冴子には 食事が続いたのです。
ゆっくりと 味わって食べました。
特に 和食と違って 一品ずつ 持ってくるのが 冴子には 新鮮でした。
食事が終わると 仲人は ふたりだけで 映画でも見に行くように 勧めました。
冴子は そう言うものかと思って 登に付いていきました。
何もわからず 登に付いていきました。途中 何か登が 冴子に言いましたが 「はい」と 答えておきました。
駅の近くの 映画館で 洋画を見ました。
あまり興味がなかったので 眠たくなりました。
最初に 広告の映画で 婚約指輪は お給料の3ヶ月分と 映し出しておりました。
それから 喫茶店で コーヒーを飲んで その店の前で分かれて 帰りました。
父親は 感想を聞いてきましたが 「特にない」と 答えておきました。
翌日 会社に行くと 上司が 昨日のことを 事細かに聞いてきました。
冴子は あったことは 細かに言いましたが、 感想については 特に ありませんでした。
それから 数日経ったら 登の方から 家に来て欲しいと 直接 電話がありました。
冴子の 父親が まず電話にでたのですが 丁重に 言われて 冴子にかわりました。
冴子は 断りたかったですが 父親が 目配せをするので 承諾しました。
あまり乗り気ではなかったのですが 父親が言うので 承諾して 次の日曜日 デート?することになりました。親が言うので 服を買って 美容院に行って 清楚な感じで 勝負する事になりました。
朝11時に 先日分かれた 喫茶店で 待ち合わせにと言うことになっています。
冴子は 家族にせかされ 30分前に 喫茶店に着き 待っていました。
11時を 少し過ぎたとき 登は 自家用車に乗って 喫茶店に到着です。
出来の良い 三つ揃いを 着ていました。
喫茶店での コーヒーもそこそこにして 自動車に乗り込みました。
その間 登は ほとんど話しませんでした。
冴子も 時候の挨拶程度で ほとんど話をしませんでした。
自動車の中でも 会話は ほとんどありませんでした。
登の家に着くと 登の家族が 総出で 出迎えてくれました。
会社の作法クラブで 習ったように 冴子は 振る舞いました。
そんな振る舞いに 特に登の母親は 感心しました。
登の母親に気に入られて 母親は 冴子に いろんな事を聞いてきました。冴子は 普通に答えていました。
食事が用意され 頂きました。
フランス料理ではないけど 和食で 豪華でした。
登は いつも食べている様子で 冴子は 心の中で 「お金持ちはこんなもの毎日食べているのね」と 思いました。
1度目にはわかりませんでしたが 登の家は 水洗便所で そのうえ アルミサッシ ステンレス流しで 冴子は 本当に びっくりしていました。
とくに 応接間には 本物の 暖炉があって 登が 小さいときは この煙突から サンタクロースが 来ると 信じていたと 話をしてくれました。
冴子は 今まで 何も 考えていなかったのですが 登のことが 段段と気になってきました。
それから 登からのデートの誘いに 従うことになりました。
でも 冴子は 2回に1回は 登の家に行くことが この先 暗雲が あることを 示していることに 気が付かなかったのは 冴子の若気のいたりでしょうか。
冴子は デートを重ね 婚約する運びになりました。登じゃなくて 登の母親が 仲人のことや 結納・結婚式・新居のことまで すべて決めました。
冴子は めんどくさがりだったの 別に 嫌のこともありませんでした。
新居も 登の家の近くの 登の父親が持っている マンションの 一室に決まりました。
1階の南向きで 専用の駐車場もあって 2DKの 当時としては広い 新しいお部屋でした。
エアコンも付いていました。
結納でもらった お金で 花嫁道具も 登の母親が こんなものが良いという 一覧表をまで 作ってくれました。
父親は 少し憤慨していましたが 「まあまあ」と みんなが言って その場は治まりました。
冴子と登との 結婚式は 昭和47年の 春でした。
日にちは 3月3日のひな祭りの日 近くの 文化会館で 盛大に行われました。
衆議院議員の先生も 来賓として 挨拶して あまりにも 立派ので 新婦側の来賓は 少し困惑したものです。
新婚旅行は 当時は 南九州が主でした。
それなのに 登の父親が 全額出してくれて あまりにも豪華な ハワイ旅行に行きました。
伊丹空港から飛行機で 出発しました。
窓から見える 伊丹の景色を 登は その時は説明してくれました。
ハワイでは 英語がわからず 旅行としては あまり楽しめませんでした。しかし、 冴子は そんなことは 新婚旅行には 関係ないので 登と 充分に 楽しみました。
伊丹空港には 登の両親が迎えに来ていて まずは 実家に連れて行かれました。
「疲れた」と言った 登は その日は 実家に泊まってしまいました。
冴子だけが 歩いて 数分の 誰もいない新居で 初めての夜を過ごしたのです。
冴子は 結婚の 2ヶ月前には 4年弱勤めた 会社を 辞めていましたので 翌日は 朝から 旅行の荷物の整理や 買い物 洗濯 お掃除をこなして 夕食の準備をしていました。
7時過ぎに 登は帰ってきて 無口に食事をして お風呂に入って テレビを見ていました。
登は 冴子の父親が勤める 会社と取引のある 部品会社に勤めていました。
当時は 半導体が出始め それが ICへと 発展していく段階で その営業をしていた 登の仕事は 忙しくなっていきます。
当時は 「猛烈社員」 と言う言葉が 流行していて 登は その代表選手に なりたいと思っているようでした。得意先の会社にだけ 営業に行くだけでなく その担当者や 上司・社長の家まで 夜討ち・朝駆けの 仕事です。
朝は 6時頃でかけ 夜は 10時頃は早いくらい 翌日になることもしばしばです。
日曜日も 接待ゴルフで いないことも多いのです。
朝ご飯は 急ぐと言って 食べずに行くことも 多かったのです。
その上 盆暮れの休みは 登の実家に行っていて 家にいるのは 寝るときだけとうのが 事実です。
冴子は 仕事だから 仕方がないし 家族のためにがんばっているんだと 言い聞かせて 諦めていました。
一年経った 昭和48年の春に 女の子が生まれました。
冴子は ひとりで 育てるのは 不安でしたが その不安は 子供が生まれると すぐに 吹っ飛んでしまいました。
何かにつけて 家にやってきたり あるいは 実家に 呼んだりして 赤ちゃんの世話をしてくれました。
登の母親だけではなく 登の父親も 「育児」に 熱心でした。
登の両親が 赤ん坊の世話をしてくれることは 冴子にとって よく言えば 育児の煩わしさから 開放されて 非常に助かっていると 考えなくもありません。冴子は 最初の内は そのように考えていました。
確かに 育児は大変です。
登が 仕事に忙しく 全く協力的でないので もし 両親の助けがなかったなら 育てられなかったと 思っていました。
そんな日々は 続きました。
赤ちゃんが生まれた年の 秋には あのトイレットペーパー騒ぎが 置きますが その時も 両親は 赤ちゃんのためにと 多量の 紙を 車で持ってきてくれました。
石油危機があっても 登の会社は 発展していきます。
半導体から IC そして LSI その先の ITバブルと 発展していきます。
登は 天性の素質があったのか 会社一途の仕事ぶりで 結果として 出世していきます。
重要なポストに就くので また仕事熱心となる 「悪循環」に陥っていくのです。
悪く言えば 家族を顧みない 良く言えば 家族のために 尽くしている 登は いずれにせよ 帰ってきて 風呂に入って 少しだけ 夜食を食べて 寝る そして 朝早く起きて 新しいカッターシャツに着替えて 食事もそこそこで出かけていくのです。そんな毎日で 休みも 初めのうちは 登の実家に行っていましたが 数年後は 会社のために出かけていくようになりました。
冴子は 経済的には 豊かで 家も 子供が ふたりできると 登の父親が 持っている土地に 新しい家を建てました。
当時としては 珍しい 3台も入る 駐車場付きでした。
そんな大きな部屋で 過ごすことになります。
そしてその 家族の内 必ずいるであろう 子供も 冴子の家には あまりいなかったのです。
冴子の子供が 幼稚園に行くようになると まず 登の両親の家に帰って おやつを食べ そして 夕食も食べて 家に帰ってくるのです。
冴子も 夕食を 登の実家ですますことも多かったのです。
結婚して 7年経ちました。登は 会社では 一番出世で 生え抜きでは 出世頭で 羨望の的でした。
会社には 生え抜き組と 天下り組の 二組があって べつに対立しているわけではありませんが 生え抜き組は 登を応援していました。
その応援に応えるべく 無理をしていたかもしれません。
朝早くでかけ 夜遅く帰ってくる 帰ってこないときも 時々ある始末です。
子供は 小学校へ行く年齢に なっても 父の日の 父親参観の日も 運動会の日も 学校に行ったこともありません。
冴子は 大きな家で 帰ってこない登と 登の家に遊びに行っている子供を ズーッと ズーッと 待っていました。
子供は 帰ってきますが 登は帰ってきません。
相談する相手もなく 冴子は 孤立していました。
家にいてもすることがないので 午前中は スーパーマーケットまわりをしていました。
自転車で遠くの お店まで行っていました。
そんな遠くのお店の パン屋さんに行ったとき その パン職人が 見たことのある顔だったのです。
冴子にとっては 因縁の人でした。高校の時に 思いを寄せていた 男子高校生です。
どんな巡り合わせかと 想いました。
冴子は 忘れるはずがありません。
11年が経っていますが その容姿は 昔のまま 精悍な どことなく 不良ぽい そんな 男性です。
コックコートを 何となく 不良ぽく 着ていました。
どこが不良ぽいのかと 考えても わからないのですが 冴子には そんな風に思えるのです。
そのパン職人は 冴子のことは 全然わからない様子でした。
じろじろ見ていたので 不審者とは思っていても 自分に思いを寄せていた人とは 気が付きませんでした。
冴子は あまりやることもないので 時間さえあれば 毎日のように そのパン屋さんに 通っていました。
そのパン職人は 名札を見なくても 覚えていますが 佐伯勇治と 言います。
勇治は 店の中では 何か浮いているような 存在で 仕事は テキパキとしているようには見えましたが 何か違っているような 感じがしました。
パン屋に通うようになって 冴子はもとより 子供も 登の両親も そしてたまに朝食を食べる登も パン食が多くなりました。食パンから始まって ぶどうパン クロワッサン あんパン メロンパン カレーパン 焼きそばパン そんなパンの オンパレードです。
登の両親は 少し不審に思いましたが 食べ慣れると これが美味しい やみつきになって仕舞うのです。
特に子供には 受けていて それを口実に 毎日 パン屋に通うことになります。
勇治は すぐに 常連客の 冴子に 気が付いていました。
そして 勇治の方を チラチラ見るので 勇治も 気になっていました。
冴子は 子供の時は 普通の 女の子でしたが 30近くなって 閑な上に お金持ちだったので 普通の女性ではなく 少し目立つ 女性になっていました。
服装も 良いものですし お化粧も 美容部員の助言に従って 極めていました。
誰もが 一目置くような 女性になっていたのです。
目立つ冴子が 毎日 パン屋さんに行ったので 勇治は 冴子が 自分に 気があるのではないかと 思い始めました。勇治も 冴子が来たときは 奥で働いていても なるべく外に出てきて 用事もないのに 商品を 整理していました。
1ヶ月が経ったとき いつものように 冴子が来ました。
勇治は 初めて 「いつもありがとうございます。」と 言いました。
冴子は 「美味しいので 、、、、」と 答えました。
それから 行くつど パンについて いろんな事を 話すようになりました。
決まった時間に 冴子は 行くので 勇治は 待っているようです。
そんなことが 数ヶ月続いて ある日 勇治は 「今度の 日曜日 ドライブでも行きませんか?」と 言ってきました。
冴子は 日曜日は 子供もいるし もしかすると 登もいるので それは無理だと思いましたが どうせ 子供は 登の実家に行っているだろうし 登は 接待ゴルフに違いないと思って その場は 約束しました。
冴子は これを待っていました。
自分から 言わなかったのは 内気な冴子の性質かもしれませんが 三十近くなった冴子は もうそんなに 子供ではありません。
家に帰って 子供たちに 日曜日のことを それとなく聞きました。
もちろん子供たちは まだ先の日曜日のことなど 予定がある訳でもなく わからないと言うことでした。
登の帰宅は遅く 起きて待っていると いつものように 疲れたように帰ってきて お風呂に入って ちょっと夜食を食べていました。
これも またいつものように あまり会話もなかったのですが 日曜日の予定を聞くと いつものように 接待ゴルフでした。
冴子は しめしめと考えました。
冴子は 美容院に行って それから ドレスアップして 次の日曜日 約束の映画館へ 行きました。外国の映画を見て それから食事をして そして お話をイッパイして 分かれました。
高校の時のことは 聞きませんでした。
パン屋さんに なぜなったのか 聞きました。
勇治の話では 大学に行ったけど ちょっとした不祥事があって 大学を辞めたそうです。
勇治は その不祥事については 言いませんでしたが 冴子には 何となく 予想がつきました。
それで 就職することになったのですが 当時は 就職難で 手に職を付けた方が 良いのではないかと パン屋さんの道に進んだのです。
そんな話を聞きながら 冴子は 勇治が 好きになって仕舞いました。
そして 2度目 3度目のデートを 続けるのです。
4度目のデートの時 冴子は ズーと気になる 事を 何となく 勇治に聞いてみました。
4度目のデートは パン屋さんがお休みの 水曜日でした。神戸の 異人館に 行くことになっていました。
三宮で 会って トアロード(東亜道路)を上って 異人館へ行きました。
いろんな異人館をまわって 風見鶏の館の近くの 喫茶店で休憩になりました。
さっきまで見ていた異人館に 住んでみたいとか 住みにくいとか 景色が良いとか すきま風が入ってくるとか そんな話をした後 冴子は 聞いてみることにしました。
冴子: 勇治さん お話があるんです。
勇治: 何の話ですか。
冴子: 今から11年前のことです。
勇治: そんな前のことを えーと 高校の時かな それとも大学の?
冴子: 高校生の時 2月の18日の時です。
勇治: そんな昔の話し 覚えていないよ はっきりした日だけど 何があった日なの 大きな事件でも起きたの
冴子: 事件など起きていません。 私は 朝早く 試験に行くために 電車に乗っていたのです。
勇治は 不思議そうに 冴子の話を 聞きました。
全く その日付に 覚えがありませんでした。
全く言われた日付に 覚えがない勇治を 冴子は 残念に思いました。「何も覚えがないなんて どういう事なの
あんな大事な日なのに 何で覚えてないのよ
勇治のバカ
でも やっぱりあのときのことを 聞かないと 一生が始まらない」と 心の中で考えながら 冷静に 聞く方法を 考えていましたが 思いつきません。
黙っていると 勇治が 「どうしたの その日が どうしたの
僕が関係あるの」と 聞いてきました。
冴子は 思わず 何も考えることなしに 「あの朝 一緒にいた女性は 誰なの」と 直球で 聞いてしまいました。
勇治: 一緒にいた女性って
いつの女性
冴子: 2月18日の女性のこと
勇治: 11年前の 覚えていないな
冴子さんは その女性と 僕が一緒にいたところを 見たんですか
冴子: 見たのです。 髪の毛の長い女性です。
勇治: 冴子さんは そんな昔の 私を 知っているんですか
どういう事なんですか
そう聞かれて 勇治は 11年前の 出来事を 話しました。
詳しく話したので 当時 冴子が 勇治を好きなことも 話すことになりました。
勇治は黙って 聞いていました。勇治は おぼろげながら その日のことを 思い出しました。
勇治: わかった わかった
そう言う理由なのか
よくわかったよ
そう言えば そんなことも あったような気がする。
たぶん その女性 いや 女子高生は 野球部の マネジャーで いや違った 元マネージャーで 高校の追試験を 受けていた人じゃなかったかな。
僕は 冴子さんが知っているように 野球部だろ
マネージャーが 学期末試験で 欠点を取って それでは 卒業できないから 早朝勉強を 元野球部員全員が 助けていたんだ。
それを 冴子さんは 見たんだね。
でも たぶん 僕の 早朝勉強は 一日だけだったように 思うんだけど
その日だけだったんだよ
それを 聞いた 冴子は 誤解だったとわかりました。
そんな誤解が 冴子の 人生の はじめの部分を 狂わしたのです。
勇治も 事のすべてを 理解でき そんなに 好かれていたことを知って 急に 冴子が もっと愛おしくなりました。冴子の方も 誤解して 恨んでいたけど 恨みは一瞬に晴れて 高校生の時に 心は戻ってしまいました。
ふたりは 誰から言うのでもなく 結ばれてしまいました。
勇治は 独身ですので 自由ですが 冴子は 夫も子供もいる身 不倫という言葉が まだ一般的でなかった時代です。
「金妻」が流行した 昭和58年より 4年も早かったのです。
勇治は 冴子が 結婚していることまでは 知りませんでした。
勇治は 冴子が 優雅なお嬢さんだと 思っていたのです。
みんなにばれなかったのは 冴子は 子供が家に帰るときまでには 必ず 家に帰っていたからです。
そんな ふたりの関係は 数ヶ月続いたのです。
登は全く気付いていないようでした。
登の母親は 少し不審には思っていたのですが 冴子のことなんか いない方が 良いと思っていたので そうなったら 好都合と 考えていたフシがあります。
みんなに気付かれずに 月日が過ぎました。そんなある日 電話が 実家からかかってきました。
父親が 緊急入院したというのです。
勇治に会う日でしたが 取るものも取らず 近くの病院に行きました。
父親は 腹痛のため 近くのかかりつけ医に行くと 大きな病院に行くように言われて この病院に来たそうです。
CT撮影すると 明らかに 問題のある 映像で 家族と一緒に呼ばれて 膵臓ガンと 宣告されてしまいました。
相当進行しており 即座に入院が決まったそうです。
6人部屋に入院している 父親を 最初に見た冴子は 痛々しそうで 見られませんでした。
鎮痛剤を使っていても 相当痛そうで 苦悶の様相です。
遅れて 兄や弟も来て 久しぶりに 家族全員が 揃いましたが こんなことで 会うのは 全く心外です。
遅れて 父親の 会社の面々も やって来て 病室は イッパイになっても 父親の痛みが 去ることなどありませんでした。
とりあえず 家に帰って まず勇治に連絡して それから 登の母親に そのことを話しました。
母親は 「子供のことや登のことは 私に任せて あなたは 父親の看病をしなさい」と 言ってくれました。
その日から 登と子供は 母親の家で 生活することになりました。
父親の病状は 良くなることはありませんでした。薬で寝ているとき以外は 痛そうで 冴子は なすべきこともなしに ただただ 見ているだけでした。
個室にかわると 夜も 冴子は 付き添いました。
父親の 膵臓ガンは 末期で もう対処療法しか ない状況でした。
痛みを 和らげるために 麻薬を 少しずつ点滴するために器具が取り付けられていました。
食事も あまり取ることができず 寝ているときが多いようでした。
お医者様は 余命1ヶ月と 宣告されていましたが それから 2ヶ月 夕日が見える この病室で 暮らすことになるのです。
登や子供も何度か 見舞いに来てくれました。
勇治には 本当のことは言わず 少し忙しいからと言って 会っていませんでした。
そんな日続くと 登や子供は だんだんと 離れていくような気がしました。
登が離れていくと 冴子の 心の中に 勇治が入ってきました。父親の病状を 勇治に話すと 勇治も 見舞いに来たいと 言いましたが まだ登のことを 話していないので 困ってしまいました。
なんだかんだと 理由を付けて 来ないようにしたのですが だんだんと 勇治は 冴子に 何かあると 思い始めたようでした。
冴子は 真実を 勇治に 話さなければならない 時が来たように 思い始めました。
父親が 少し安定して 下の弟が 一日 付き添うというので 体が空いたその日 勇治の 休みと 重なりました。
冴子の家には 登や子供は 帰ってこないので 心配せずに 勇治の電話を 受けることができました。
そして その朝かかってきた電話で 「会って話したいことがある」と 約束して その昼 駅前の喫茶店で 会う約束をしました。
冴子は いつもの 少しケバイ服装ではなく シックな服装で 化粧もほとんどせず 薄く口紅をつけて 結婚指輪を 左手の薬指にはめて 喫茶店に向かいました。
喫茶店には 早い目に行きました。勇治は普通は ほんの少しだけ 遅れて やってくるのが 普通ですが その日だけは 時間どおりに来ました。
勇治は 冴子を見るなり 「今日の冴子さんは何か違うぞ」と 思いました。
どことなく大人っぽくなっていて 本当の 冴子のような気がしました。
勇治: 話があるって何
冴子はそう聞かれて まず左手を 見せました。
そこには 結婚指輪が 輝いていました。
勇治は おそるおそる聞きました。
勇治: その指輪は
そう聞くのが精一杯でした。
冴子: ごめんなさい。
私本当は 結婚していたんです。
嘘をついてごめんなさい。
あなたにあったとき そう言えば良かったのに
でも 言えなかったんです。
ごめんなさい
勇治: そうなんですか
僕も 何となくそうではないかと 思っていたんだ
そうなら でも 、、、、、 でも 今は ひとりで住んでいるんじゃないの
冴子: 父親が病気のため 主人と子供は 主人の実家に行ったきりなの
でも それを なぜ知っているの
勇治: ごめん 少し調べたんだ 電話番号から
冴子: そうなの
勇治: はっきり聞くけど その主人と僕 どちらが 好きなの
僕は 金持ちの 遊びだったのか
勇治の声は 大きく 冴子に響きました。
冴子も すぐさま 少し声を上げて
冴子: もちろん 勇治さんです。
それだけはわかって欲しい 勝手な言い方だけど
勇治は 冴子が 結婚していて がっかりしました。でも 冴子と 登との関係が あまり良くないと 聞いて 少し安心しました。
勇治は 不良ぽい性格です。
勇治は 禁じられた恋になって 余計に 好きになるタイプです。
冴子が 結婚していたと聞いても 会って欲しいと 勇治は 告げいました。
ふたりの関係は このまま続きます。
冴子の父親の 病状は 悪化する一方です。
冴子が 病院泊まり込む日も 連日になりました。
冴子が 付き添ったからと言って 病状が軽快するわけではないのですが そうするしかなかったのです。
唯一 父親は 冴子が 泊まっていると 喜んでくれました。
最後には 勇治も見舞い行くることもありましたが 父親は傷みのために寝ていて もちろん会うことは出来ませんでした。
そんな毎日が 続いて 父親が危篤となりました。
家族全員が呼ばれて 病室に集合しました。
登も 子供も集まって 面会時間が 終わる頃になって 父親の体に付いている 心電図が 平坦になって仕舞いました。
父親の お葬式は 準社葬になっていて 会社の 総務課が仕切っていました。家族は 世話役の言うとおりに やっていました。
冴子は 通夜の晩は 夜通し いました。
会社優先の 登も お葬式とあって 忌引きを使って 休みを取り 登の家族や親戚も 参列しました。
ビデオを撮っていて お葬式の様子を 後から見ていると 冴子は うち沈んでいるように見えました。
子供は あまり知らない おじいさんなので お葬式の時も やんちゃなことをしていました。
それから 参列者の中に 勇治が映っていました。
多くの人の中に 映っていますので よく見ないとわからないような うつり方でした。
初七日が来ても 冴子は 父親の家に 泊まっていました。
10日過ぎても まだいました。
早く帰るようにと 母親に言われたので 帰ることになりました。
もちろん歩いても帰れるような 距離ですが 帰りました。
家には誰もいませんでした。
玄関の 靴入れの 靴も少なくなっていました。
冴子は 登の家に 行って 今までのお礼を言って また登や子供が帰ってくるように お願いしました。登の両親は 「それがいい」と 言いながら 実際は 子供は 時々しか 家に帰ってこないし 登も なんだかんだと理由を付けて 帰ってきませんでした。
そうしている間も 冴子は 勇治のパン屋さんに行って それとはべつにと 会っていました。
そんな日が 1ヶ月くらい続いた日 思い出したくもない 人間から 電話がありました。
名前も思い出したくもないので 冴子は Pと呼んでいました。
pはイニシャルではなく 「屁の様な人間:プー」からきています。
Pは 中学校の時に 冴子の スカートをめくった 張本人のことです。
声も聞きたくないのに 電話をしてきたのです。
電話の向こうで 名乗ったとき 切ろうとしました。
でも Pは 「冴子の真実を知っているのだ」と 言ってきました。
会いたくもないPは、 強引に 「電話を切るな」と 言うような意味を 言ってきました。何で 電話かけてきたのか わかりませんでした。
Pの話を 要約すれば 「冴子の父親の葬式に 社命で出席した。
その時 冴子を 見ていると 冴子が ちらっと見る男性がいた。
そして その男性も 冴子を 見ていた。
不審に思っていたが 偶然喫茶店で会っている 冴子とその男性を見かけた。
冴子は不貞をはたらいているんじゃないか?」と 言うものでした。
当時は 不倫という言葉が まだ一般的でなかったので 不貞 もっと古典的な言葉の 不義密通 と言う言葉が使われていました。
冴子は 言い当てられて 言葉もありませんでした。
冴子は 開き直って 「だったらどうするのよ」 と言い放したい気持ちでしたが 勇治に迷惑がかかっても 大変なんで 「そんな事ないです。
会って そんな誤解を 解きたい」と 言うのが精一杯でした。
「それは誤解」と 言った冴子の 言葉を Pは 全く信用する様子はありません。しかし Pは 別に 冴子を どうしようと 考えているようでもないのです。
どうも Pの真意は わかりません。
そんな なんだかわからない 電話は 切れました。
心配だけが残こりました。
これからどうすればいいのだろうかと 冴子は 思いあぐねていました。
勇治との 関係を 断とうかとも 思うのですが そんなことは できないのです。
どうすることもできない ジレンマに陥ったのです。
そんな日々が 過ぎていきました。
日々が過ぎても 登は 時々しか帰ってこないし 子供は 昼間は 行ったきりだし ひとり どこにも行かずに 家にいました。
心配なので 毎日 行っていた パン屋さんにも行かないし もちろん 勇治とも 会っていませんでした。
ズーとあとで わかったことなんですが Pは 登の会社の仕入れ先で 冴子から 登に うまく言ってもらって 取引量を 増やしてもらいたかったのです。そんな 下心だったんですが うまく行きそうもないので 冴子には 近づいてこなかったのです。
冴子は 不安でした。
そんな日が 10日過ぎた日 午前中 子供は学校に 登はもちろん 会社に行っているその日 家で あてどもなく掃除をしていると インターフォンが鳴りました。
「誰かしら」 「もしかして」と 考えつつ 出てみると 勇治でした。
勇治は パン屋にも来ないし 電話もないし 電話もできないし 家にやってきたのです。
家の中で 会うのは どうかと思ったので 外で会うことにしました。
誰もが知らないだろうと思う 路地裏の 喫茶店に 行きました。
思い切って 勇治に Pのことも 話しました。
話さないと 信じてもらえないと 思ったからです。
少し涙が 冴子は出そうになりました。
そんな 冴子を見て 勇治は 胸が詰まりました。
そして どちらから言うともなしに 2人の考えは ひとつになったのです。
「冴子が 登と別れて 勇治と 暮らす」 という話しになって仕舞ったのです。普通?に 結婚生活をしていて ふたりの子供もいる 冴子が 急に 離婚を決意する そんな 突然の 、、、、
冴子自身 びっくりしてしまいました。
もちろん 勇治という 味方がいるから そんな決断ができるのかと 思いました。
冴子は 「登はどうせ 私のことなど 眼中にない会社人間だし 子供は 私よりおばあさんの家の方が好きだ様だし 、、、、」 と 自分に言い聞かせて そんな決断をしたのです。
もうどうにでもなれという 心境だったのかもしれません。
そう決断すると 行動は早いです。
勇治が パン屋の勤め先が 神戸の方にかわるのを 機会に 突然いなくなると言うものです。
転勤は 二週間ほど先です。
ふたりで神戸に行って 新しい お部屋を探しました。
昔 登と行った 異人館の北野辺りに 勇治は住みたいと言いましたが 冴子はいやだったので 長田の尻池周辺の アパートを 借りました。
そんな 何となく決めたことが 後々 大きな 結果になって仕舞うことを 冴子は 知るよしもありませんでした。
冴子が 家を出たその日は 秋の良く晴れた日で 昭和54年29歳の時のことです。冴子は 市役所からその日のために もらってきた 離婚届に 名前を書き 判子を押しました。
それと 登のお給料を 入れて貯めていた 通帳と 判子も置いておきました。
置き手紙も 書いておこうと 思いましたが 書くことができませんでした。
思いつかなかったのです。
冴子が 独身時代に 貯めていた 通帳と 当座の服と 少しの身の回り品だけを バックに詰めて 家を出ました。
鍵は いつもはしないけど 郵便受けに 入れておきました。
ふたりの子供には 申し訳ないけど 家に 「さようなら」と 言って 家を後にしました。
近くに 勇治は 車で迎に来ていました。
バックを 手際よく トランクに入れ 走り去りました。
勇治の 荷物は 前日に 引っ越し屋さんに頼んで 神戸に送っていました。
神戸までの 車の中で 冴子は これからの どのようなことが起こるか 心配でした。
勇治との 楽しい生活は 予想できましたが そんな幸せのために ふたりの子供を 犠牲にしてもいいのかと 心の中で 悩んでいました。
悩みながらも 勇治との生活を 楽しみにしていました。勇治は パン職人として 新しい店に 勤め始めました。
冴子は 専業主婦として 勇治を 助けることになりました。
働きに出て 登の家族に 見つかるようなことがあったら 困るからです。
今まで 大きな家で 専業主婦をしていた 冴子が 6畳一間の アパートで 専業主婦になったのです。
掃除機を使わなくても 掃除も簡単で 共同の洗濯機で チョイチョイと やっていたのです。
冴子は 結婚するまで 小さな家で暮らしていたので 平気だと思っていたのですが 暮らし初めて やっぱり 小さい部屋は 置く所が無くて 不便と 思いましたが そんなことは 心の中にしまっていました。
小さい部屋でも 勇治は 必ず 登と違って 時間になると 帰ってきました。
それが幸せだと 冴子は思いました。
でも 一ヶ月経った頃 少し失敗したと 勇治と話すことになります。
勇治のお給料を 引っ越して来たときに 全額もらって お小遣いとして 3万円を渡しました。お給料は 手取り 13万円で 残った 10万円を使うことができると 考えていました。
冴子は 結婚していたとき いや今も結婚していますが 前の結婚していたとき 食べ物には 気を使っていました。
無農薬とかに 凝っていたときもありました。
住んでいるアパートの近くには そんな食品を 扱っている お店がないので 遠くまで 通って 買っていたのです。
月末になったときには 3万円弱になっていました。
あと 10日ほど 「これで生活できるかな」 と 考えていたとき 勇治が 「家賃を払っといて」と 夕食が 言ったのです。
冴子は 「えっ 家賃? いくらなんですか」 と 勇治に尋ねました。
冴子は 独身時代は 親と一緒に住んでいたし 結婚したときは 親が出してくれていたし それから 持ち家になったので 家賃という 考えがなかったのです。
残っているお金では 払える額でないことは わかりました。
冴子は 登と 勇治は 結婚生活でも 全く違うと思いました。
とりあえず 冴子の貯金から 家賃は払っておきましたが 冴子は 経済的なことを 考えないと いけないと 思いました。
勇治はよく 「いつかは自分のパン屋さんをやってみたい」 と話していました。冴子は 働くことにしました。
お金を貯めて いつかは パン屋さんを ふたりで するんだと 勇治と 話しました。
働いて そして 節約して お金を 貯めようと ふたりは決意しました。
勇治の小遣いも 1万円にして 残りを 貯金することになりました。
勤め先で 残ったパンを 持って帰る 日々が続くのです。
冴子も 探しました。
でも 何の特技や 資格もない 冴子には 働き口が 容易に見つかることはありません。
職安から帰る途中 家の近くで ウェートレス募集の 張り紙がある 喫茶店がありました。
冴子は わかりませんでしたが 飛び込みました。
冴子が 喫茶店に入ると テーブルに向かって 多くの客が テレビゲームをしていました。
店主らしき 男性が いらっしゃいませ と冴子に言いました。
冴子は 「表のチラシで 来ました」というと 店主は 冴子を 上から下まで見て 「時給は350円 明日からでもいいよ。
もう少し 化粧をして来れるなら」 と言われました。
当時は 喫茶店でする テレビゲームが 流行始めた頃で 人手が 必要だったのです。
勇治に話すと 家の近くで あまり出歩かないので 見つかることもないだろうと 承諾してくれました。
朝の 9時頃出勤して 4時頃まで 仕事で 途中1時間休んで 6時間の働きです。
日給2100円 です。
工場の 工員さんが 多かったので 日曜日は 冴子は 休みになっていました。
月に 5万円弱の パートタイマーです。
喫茶店での仕事は 単一な仕事でしたが 意外と 一日が終わると 疲れる仕事でした。
冴子は ながく 専業主婦をしていたからと 思いました。
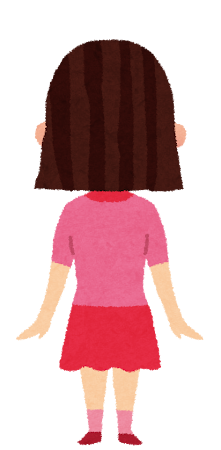 疲れて 家に帰っても 休んでいるわけにはいきません。
疲れて 家に帰っても 休んでいるわけにはいきません。勇治が 帰ってくるまでに 夕食を作ります。
安い食材で ボリュームがあって 美味しいものを 作ることになっています。
テレビや 雑誌を参考に 作ります。
勇治は 6時の定時になると 必ず帰ってきます。
まずお風呂に入って それから食事です。
なにぶん狭いお部屋ですので 食卓は 折り畳み式になっていて 勇治が 広くすると 冴子は 作った おかずとご飯 そして汁物 それと 勇治が持って帰ってきた パンを並べます。
外見だけでみると 豪華でした。
勇治は 美味しい 美味しいと 言って食べてくれますので がんばって作るのです。
それから 職場も 最初に働いたところのように 気むずかしいところが無くて よかったと 思いました。
子供には 申し訳ないけど 家を出て 良かったと思いました。
そんな冴子が 働きやすい 喫茶店の 店長は 今で言えば ちょっとした セクハラをしていたみたいです。
冴子の働いている喫茶店は 純喫茶店ではありません。純喫茶店以外に 何があるかというと もう少し時代が進んで ノーパン喫茶とか そんな風なところでしょうか。
冴子が勤め始めた頃は スカートが段段と 短くなって頃で 段段極端になっていた頃です。
店長が 突然 ミニスカートを 制服にすると 言ってきたのです。
他の 働いている仲間と 「絶対反対同盟」 を作って 対抗しましたが 少しだけ 長いスカートに なって 決着しました。
冴子は 困った店長だと 思いながら でも 資格や職歴がない 自分は ここで がんばって働くことになります。
店長だけではなく 客の中にも 困った人がいましたが うまくやり過ごすように していました。
ところで 冴子は 喫茶店に置いてある テレビゲームを したことがなかったので 休みの日に 勇治と 違う喫茶店に行って やってみることにしました。
インベーターゲームです。
100円を入れると 3回できるのですが 勇治は やったことがあるらしくて 割りとうまいのです。
冴子に こちらで移動して こちらで撃つのだと 言われてやり始めましたが すぐにやられて 3回は終わってしまいました。
10秒ほどの間です。
「何が面白いのよ」と 冴子はつぶやきました。
冴子は インベーターゲームが あまりにも すぐに終わったので 面白くありませんでした。勇治は 相当うまく 何万点と 取るのです。
練習のたまものかもしれません。
1万円のお小遣いで よくできたものだと思いました。
聞いてみると 勇治は 一日に 200円と決めていて それ以上は 使わないそうです。
勇治は運動神経が 良いんだと 思いました。
でも 運動神経と インベーターゲームとは 関係がないかな と 心の中で思い直して 少し笑ってしまいました。
でも この 勇治の 「運動神経?のよさ」が 将来困ったことを 起こすのです。
逃げるようにし 結婚した日から 1年が経った頃 勇治は 「子供が欲しい」と 言ったのです。
冴子は 勇治のことが よくわかりましたが 子供のことは 何か わだかまりが あるのです。
残してきた 子供が やはり心残りです。
そんなわけで 冴子は 赤ちゃんを作ることを ためらっていました。勇治は 冴子の心情も わからないではないが 冴子との間に 子供が欲しかったのです。
勇治は そのことは 二度と 冴子には言いませんでしたが 冴子と勇治が 少し離れていく きっかけとなっていくのです。
でも 仲良く暮らしていて 近所でも 評判の 夫婦なんです。
慎ましく 生活していました。
休みの日は ふたり揃って お金の掛からないところに 出かけました。
ショッピングセンターや 無料の講演会 演奏会 などを探して 行っていました。
一週間 新聞や 広報誌や ポスターなどを くまなくみて ふたりは相談して なんだかんだと 楽しく話しながら 予定を決めました。
喫茶店には 勇治が休みの日には 必ず 休むように していました。
休みの朝には お弁当を 節約材料で作って パンと組み合わせて 持っていきました。
外で外食することは 殆どありませんでした。
そんな生活をしながら 10年が経ち 元号も 昭和から 平成にかわりました。
平成になったとき それは あとでわかったのですが 不動産バブルの時期です。不動産価格が 止めどもなく上昇すると 当時の 日本国民は どう思っていました。
極端な場合 あさかった不動産が 夕方高く転売できるのです。
多くの 不動産を持っていた 大地主はもとより 小さな土地を持っていた人たちも 見かけの資産は 上がっていって みんなお金持ちになったような気になっていたのです。
土地だけでなく お給料も 一緒に 上がっていったので 消費は増えて 日本は 好景気になりました。
年寄りから 若者に至るまで 恩恵を受ける結果となりました。
勇治のお給料も 20万円を越え 冴子の時給も 350円から500円に上がりました。
単に 最低賃金が上がったので 冴子の給料も上がっただけなんですが 冴子は 嬉しくなっていました。
そんな勇治と冴子は バブルの 波の ほんの小さな 波がやってきていたので 気が大きくなっていました。
絶対に外食はしないという 原則も 少し弛められて プチ贅沢をしていました。
勇治と冴子は 一緒に バブルと言うことで プチ贅沢をし始めたのですが ふたりは 少し方向が違っていたように思います。勇治は テレビゲームから ゲームセンターへ移行し それと同時に パン屋さんへの独立です。
冴子は 贅沢をしようとして できなくなってしまうのです。
それは 勤め先の 喫茶店を 突然解雇されたのです。
理由は 店長は言いませんが 冴子に限らず誰もが 冴子が 40才近くなったことが理由です。
店では 若い店員が 入って 歳をとった冴子は 首になったのです。
でも 冴子は 別に 問題はないと思っていました。
なにしろ バブルですので 求人が多かったのです。
職安に すぐに行って 速攻で 職が決まってしまいました。
今度の 仕事は 不動産業者の 店員です。
接客と言うことですが お茶だしから 始まるそうです。
喫茶店で勤めていたというと すぐに採用になりました。
パートで 時給は 前より上がって 600円です。
冴子は 最低賃金ではなかったので 実力が認められたのかと 嬉しくなりました。
何年間か 最低賃金で 働いていた 冴子は 私たちの時期が来たのだと 思いました。冴子は 採用の決まった日 翌日から 不動産会社に出勤しました。
何千万というお金が 行き交う 職場ですが 社長や 働いている人たちは 意外と親切で 気に入ってしまいました。
冴子の仕事は 簡単に言えば お茶汲みです。
でも お茶ではなく コーヒー 本格的な コーヒーです。
冴子が喫茶店で使っていた 用具を 早速 購入するよう 言われました。
喫茶店の時 取引のあった 問屋さんに電話すると その日の内に 持ってきてくれました。
なにしろ 経費は 100万円あったので カップや 制服まで 良いもので揃えました。
翌日から 本格的な 薫り高い コーヒーを 出しました。
お客様だけでなく もちろん社員も 飲めたので 冴子は すぐに 会社の人気者になりました。
新しい会社勤めで がんばっていた 冴子ですが 車の運転免許を 取るようにと 言われました。コーヒーだけ出していたら 良いという 約束でしたが 冴子が 客当たりが良いので 案内もするように言われたからです。
今は パートで 働いていますが 案内係もやれば 正社員として 給料も上げるという約束でした。
運転免許を取得する必要があったのですが それに ちょっと 冴子は困りました。
運転免許を取るためには 住民票が 必要です。
登に 離婚届を 置いてきた時から 住民票は 見たことはありません。
今の住所に移して 結婚届を出したら 住所が ばれてしまうと 思ったからです。
でも 給料のこともあるし 一回調べてみようと思いました。
神戸から 西へ遊びに行くことはあっても 東の方へは あれ以来行ったことがありませんでした。
でも 休みの 水曜日の日に 住民票を 取りに 前に住んでいた 駅に 変装して 出かけていきました。
当時流行していた 黒い服を着て 黒の帽子 白いマスクの変装です。変装しているのが 目立つのですが 冴子は 登や登の母親に 見つからないように 駅の近くの 出張所ではなく 少し離れた 市役所まで 歩いて行きました。
冴子は 駅や道が綺麗になっていたので 時間が経ったのだと 思いました。
市役所に着いて 住民票の申請書に書いて出しました。
世帯主の欄には 登の名前を書いて出したのですが しばらくして 冴子は 受付係に 呼ばれました。
冴子の申請した住所には 冴子ひとりだけが 記載されているとのことです。
そこで 申請書を書き直して 出しました。
お金を払って 住民票を 椅子に座って よくよく見ると 冴子が 家を出た翌日に 登と子供は 母親の家に転居していました。
おそらく 離婚届を 翌日出して 住所も かえたのでしょう。
涙が 出てしまいました。
しばらく その椅子に座って 動くことができませんでした。
小一時間経った時 冴子は 我に帰って 足取りも重く 市役所を あとにしました。
冴子は 住んでいた家が どのようになったのか 知りたくなりました。
でも 見つかったら と考えつつ でも 足は 家の方に向かっていました。
足が 自然に向かったその方向には 冴子の前住んでいた家でした。二十数分歩いていましたが 冴子は その記憶があとになっても ありません。
夢中になって 歩いて行きました。
冴子は その家が見えた時 驚きました。
バルコニーに 見られない女性が 洗濯物が 干していたのです。
冴子は 登が新しい女性と 結婚したのかと 思いました。
でも ズーッと 若い人でしたし 登の 奥さんとは 似つかないような人だったのです。
門の前まで着いた時 わかりました。
表札が 河本でなかったのです。
家は 新しい人が 住んでいたのです。
詳しく調べたわけではありませんが たぶん 冴子が家を出た翌日に 離婚届が出されて 登と子供は 実家に戻ったのでしょう。
不要になった 家は 売却されたのでしょう。
冴子が いたすべての証拠をなくしたかったのではないかと 推量しました。
冴子は そんなに 憎まれていたのかと 今更ながら 思いました。
でも 自分がしたことですので どうしようもありませんでした。
憎まれて当然とも思いますが 冴子には 冴子の言い分もあるのです。でも そんなことを 登や 子供たちに言ったところで わかってもらえるわけでもなく どうしようもないことだと 諦めるしか なかったのです。
子供は 大きくなっているかなと 考えていました。
歳からすると 高校生になっているのかと 思いました。
どちらの 高校に行っているなだろう と考えても どうしようもないことを 考えつつ 駅まで帰ってきました。
そうしたら 後ろから 呼び止める 人がいました。
それは 思い出したくもない あの Pだったのです。
声だけ聞けばわかるので 無視して 改札を 通って ホームに向かいました。
逃げるようにして 電車に乗って 帰途につきました。
なぜわかったのだろうと あとになって 考えましたが そんなことは どうでも良いと考え直しました。
冴子は 「本当に あの Pは 私の 邪魔をするものだ」と 思いました。